「とりあえずNISAを始めた」その後のメンテナンス、していますか?
新NISAの開始を機に、多くの人が投資信託などを通じて資産形成をスタートさせた。しかし、「一度設定したら、あとは放置している」というケースは少なくない。確かに、長期・積立・分散投資は手間がかからないのが魅力だが、完全な放置には思わぬリスクが潜んでいる。それが「資産配分の崩れ」である。
当初、自身のリスク許容度に合わせて最適なバランスで組んだはずのポートフォリオも、市場の変動によって時間とともにその姿を変えていく。この記事では、なぜ資産配分のメンテナンス、すなわち「リバランス」が必要なのか、その具体的な方法と放置した場合のリスクについて専門的な視点から解説する。
なぜ「リバランス」が重要なのか?資産配分の放置リスク
投資の成果は、どの銘柄を選ぶかよりも、どのような資産クラス(株式、債券など)をどのような比率で組み合わせるかという「資産配分」に大きく左右されると言われている。この基本原則を理解することが、リバランスの重要性を知る第一歩となる。
当初の「最適な資産配分」とは
投資を開始する際、多くの人は「国内株式30%、先進国株式50%、国内債券20%」といったように、自身のリスク許容度や目標リターンに応じて資産の配分を決める。この比率こそが、その時点における自分にとっての「最適解」である。債券などを組み入れるのは、株式市場が下落した際のクッション役として、資産全体の目減りを抑制する目的がある。
時間の経過とともに資産配分は崩れていく
しかし、この最適なはずの資産配分は、市場の動きによって刻一刻と変化していく。例えば、株式市場が好調で株価が大きく上昇した場合を考えてみよう。当初は株式70%、債券30%の比率だったポートフォリオが、株価の上昇により、気づけば株式80%、債券20%といった比率に変わってしまう。これが資産配分の「崩れ」である。
放置が招く「リスク増大」という罠
この資産配分の崩れを放置することこそが、「放置リスク」の正体である。上記の例で言えば、ポートフォリオに占める株式の割合が増えたということは、当初想定していたよりもハイリスクな状態になっていることを意味する。この状態で市場が下落局面に転じると、資産全体が受けるダメージは当初の想定をはるかに超えてしまう可能性があるのだ。つまり、知らず知らずのうちにリスク増大を招いているのである。安定的な運用を目指して債券を組み入れた意味が薄れてしまうわけだ。
リバランスの具体的な方法とタイミング
この資産配分の崩れを当初の計画した比率に戻す作業が「リバランス」である。リバランスを行うことで、機械的に「値上がりして比率が増えた資産を売り、値下がりして比率が減った資産を買う」という、いわゆる「安く買って高く売る」投資の理想的な行動を実践できる。
リバランスの頻度は?
リバランスを行うタイミングに厳密な正解はないが、一般的には以下の2つの方法が知られている。
- 定期的なリバランス: 「年に1回」「半年に1回」など、期間を決めて定期的に資産配分をチェックし、修正する方法。年末や自身の誕生日など、忘れにくいタイミングをルール化するのがおすすめである。
- 乖離率に応じたリバランス: 「当初の配分から5%以上ずれたら」といったように、資産配分の乖離率に基づいて不定期に実施する方法。より厳密な管理が可能だが、常に市況をチェックする必要がある。
初心者や多忙な人にとっては、年に1回程度の定期的なリバランスが現実的かつ効果的だろう。
リバランスの具体的な手法
リバランスには、主に2つの手法が存在する。
1. 割合が増えた資産を売り、減った資産を買う
最も基本的な方法である。例えば、株式の比率が増えすぎた場合、その一部を売却し、その資金で比率が減った債券などを買い増して元の比率に戻す。ただし、NISA口座の場合、売却した非課税枠の再利用は翌年以降になるため、注意が必要だ。
2. 追加投資で調整する
NISA口座での運用において、より現実的なのがこの方法だ。毎月の積立投資などの追加資金を、比率が減ってしまった資産クラスに集中的に投下することで、全体のバランスを調整する。例えば、株式の比率が高くなっているなら、その月の積立は債券の投資信託に全額振り向ける、といった具合だ。この方法は非課税枠を売却で消費することなく、時間分散の効果を活かしながら資産配分を整えることができる。
NISAにおけるリバランスの注意点
NISA口座でリバランスを行う際は、課税口座とは異なる注意点がある。特に新NISAでは「つみたて投資枠」と「成長投資枠」を併用するケースも多く、ポートフォリオ全体での管理が求められる。
前述の通り、NISA口座内の商品を一度売却すると、その非課税投資枠が復活するのは翌年以降となる。そのため、頻繁な売買を伴うリバランスは、NISAの非課税メリットを最大限に活かせない可能性がある。したがって、NISAにおけるリバランスの基本戦略は、「追加投資による調整」と考えるべきだ。これにより、非課税枠を維持しながら、長期的な視点で資産配分の最適化を図ることができる。
まとめ:今すぐ資産配分のチェックを
投資は「買ったら終わり」ではない。むしろ、そこからがスタートである。市場の変動は誰にも予測できないが、自身のリスク管理は可能だ。定期的なリバランスは、長期的な資産形成の航海において、羅針盤を修正し、目的地へと着実に進むための重要なメンテナンス作業なのである。
放置リスクによる意図せぬリスク増大を避けるためにも、まずはご自身のNISA口座の現状を確認し、資産配分が当初の計画からどれだけ変化しているかをチェックすることから始めてみてほしい。

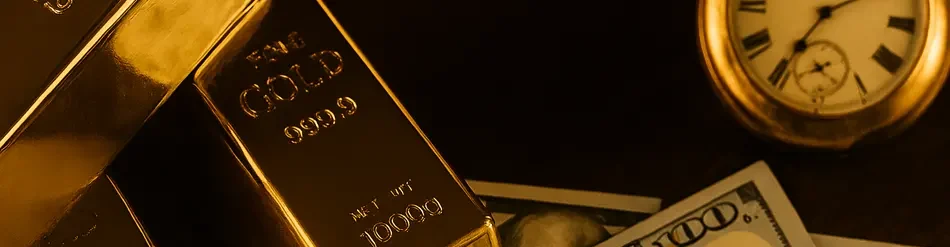
![「NISA」と「投資信託」の専門AI解説ブログ - [ Finance.ununplus.com ]](https://finance.ununplus.com/wp-content/uploads/2025/12/images-660x371.webp)